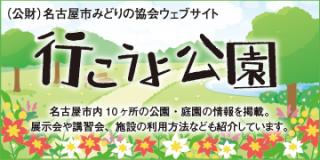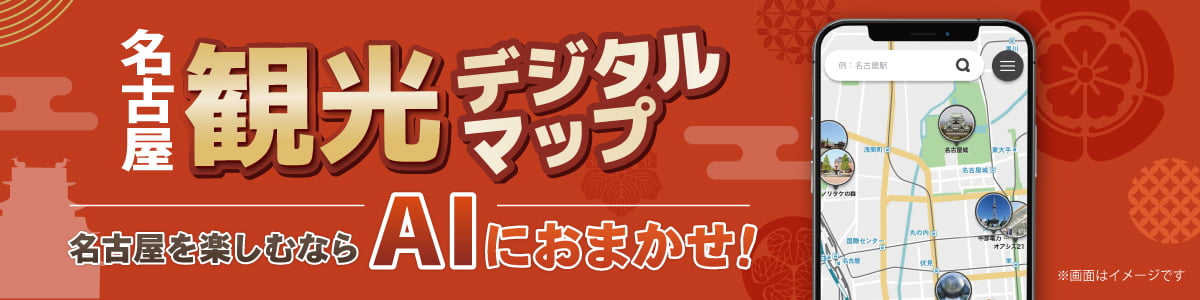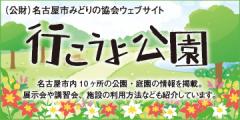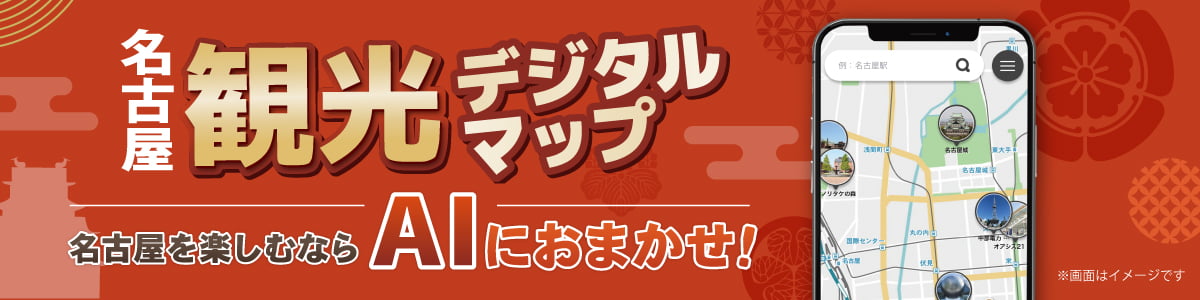徳川家康の「城下町(まち)たび」《三英傑のゆかりの地》
1610年(慶長15年)に西の砦として築かれた名古屋城。清須城を廃止して、建物をごっそり名古屋城下に大移動させたのが「清須越し」です。新しい城下町は京都の碁盤割をモデルに都市計画が行われ、現在も町並の片隅に江戸時代の風情が残っています。
徳川家康の「城下町(まち)たび」
名古屋城下町は京都がモデル!?家康のはんなり都市計画
名古屋城から南へ続く城下町を歩いてみましょう。
<名古屋~大須コース> 所要時間:約3時間

1.四間道
四間道は、城下町西部の堀川沿いに立ち並ぶ商家のエリア。物資の集散を行うため玄関は堀川側、土蔵は家の裏手に作られたため、ここでは堀川沿いに並ぶ土蔵の景色が見られます。ちなみに四間道とは4代藩主吉通の命により、商家の裏道幅を4間(約7メートル)に拡張した道のこと。名古屋市町並み保存地区に指定され、おしゃれなレストランやカフェが続々オープンすると、多くの若者が集まる人気のエリアとなりました。



屋根神様(やねがみさま)
碁盤割の城下町には多くの長屋が建ち並んでおり、新たに社を建てる空き地がなかったため、民家の屋根に小さな祠を設けて信仰していました。この屋根神様は名古屋とその周辺の町場に多くみられます。



2.伊藤家住宅
伊藤家は慶長19年(1614)に移住した清須越十人衆の商人で、現在の伊藤家は分家に当たります。松坂屋の始まりである「いとう呉服店」の伊藤家と区別して「川伊藤」と呼ばれました。建物は、江戸中期の住居と元禄期の防火建築の土蔵が見られ、堀川の水運を利用して家業を営んだ堀川筋商家の典型例とされています。

伊藤家は慶長19年(1614)に移住した清須越十人衆の商人で、現在の伊藤家は分家に当たります。松坂屋の始まりである「いとう呉服店」の伊藤家と区別して「川伊藤」と呼ばれました。建物は、江戸中期の住居と元禄期の防火建築の土蔵が見られ、堀川の水運を利用して家業を営んだ堀川筋商家の典型例とされています。
3.五条橋
五条橋は、名古屋城築城と同時に開削された堀川で初めて架けられた橋です。もとは清須を流れる五条川に架かっていましたが、清須越しの際に移築されました。
擬宝珠(ぎぼし)
堀川開削以前から存在していたという擬宝珠(橋の飾り)。現在あるのはレプリカで、本物は名古屋城に保存されています。



4.桜天神社
織田信秀(信長の父)が京都の北野天満宮に参詣したとき、夢枕に現れた菅原道真のお告げに従い創建したといわれる桜天神社。桜の大樹があったことから「桜天満宮」「桜天神」と呼ばれていました。築城の際には加藤清正がここに本陣を構えて指揮をとり、茶会を催したと伝えられています。歳の数だけ水をかけると願いが叶うという「願の水の牛」もありますよ。



天神の井戸
築城の際に清正が掘ったという井戸。そこに飾られている鷽(うそ)は「学ぶ鳥」と書くことから、受験生のマスコットとなっています。
5.朝日神社
名古屋城築城の際、家康は、豊臣秀吉の妹で正室(本妻)にあたる朝日姫の氏神である朝日神社を城下町碁盤割りの守護神として清須から移すよう請願。城下町碁盤割りの唯一の神社として崇敬を集めました。大火によって道路を拡張し「広小路通」が整備されると、これまで神社仏閣の境内で行われてきた見世物や芝居が広小路通で行われ、大繁華街となったそうです。


6.大須観音
正式には、真福寺寶生院(ほうしょういん)といい、一般には大須観音の呼び名で親しまれています。もともとは尾張国長岡庄大須郷(現在の岐阜県羽島市桑原町大須)にあった寺ですが、そのあらたかなる霊験ゆえに、家康の命で名古屋に移されました。この門前のにぎわいが大須商店街の起源。名古屋のサブカルの聖地として若者に人気です。また、毎年2回、境内で骨董市が開かれています。